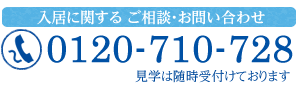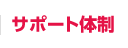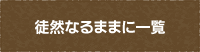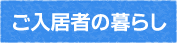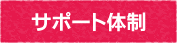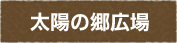【太陽の郷 動・植物だより】ムクゲ
2021/07/02
【太陽の郷 動・植物だより】ウズアジサイ
2021/06/09
【太陽の郷 動・植物だより】ハマボウフウ
2021/05/06
【太陽の郷 動・植物だより】ヤマブキ
2021/04/02
【太陽の郷 動・植物だより】アセビ(馬酔木)
2021/03/06
【太陽の郷 動・植物だより】梅
2021/02/03
【太陽の郷 動・植物だより】ヒメツルソバ(ポリゴナム)
2021/01/12
【太陽の郷 動・植物だより】ツルウメモドキ
2020/12/15
【太陽の郷 動・植物だより】ニシキギ
2020/11/05
【太陽の郷 動・植物だより】ヒガンバナ(リコリス)
2020/10/10